越智今治農業協同組合 営農指導課 堺 晃貴
1 実践テーマ
-
- (1)テーマ:
- 鳥獣害捕獲技術の向上と防護柵による作物被害軽減対策
-
- (2)対象地区:
- 今治市大西地区
-
- (3)目的:
- 当地区の主要品目は柑橘、キウイフルーツ、水稲、里芋であり、早期米の8月~かんきつの3月まで長期間作物がある環境となっている。今年度、巡回指導を行う中で、温州みかんやはれひめ(かんきつ)の食害や倒木、根の食害等、イノシシの被害が多いことを実感した。電気柵やワイヤーメッシュ柵を導入している園地もある一方で、被害が発生しているにも関わらず、対策を行っていない園地も一定数存在する。そこで、地区内の捕獲意識と防護意識、それぞれの向上を促し被害減少に取り組む。
-
- (4)協力者:
- 今治市大西地区農業者、同地区内猟友会員
2 活動経過
- (1)捕獲意識の向上に向けた取り組み
猟友会のハンターと被害発生園地周辺の現地調査(写真1)を行い、被害状況や箱わなの設置状況を確認した。そのうえで、地形や獣道の状態から箱わなの設置に適した場所を選定し、その位置に箱わなの移設を行った。移設後のわなにはクラウドセンサーカメラを設置し、誘引状況等の情報提供を行った。 - (2)防護意識の向上に向けた取り組み
①モデル園の設置
地区内にある対策未実施で食害(写真2)や、倒木被害を受けているかんきつ園地(約21a 外周230m)を電気柵のモデル園地とし、設置管理について指導を行った。
②鳥獣害対策勉強会の開催
えひめ地域鳥獣管理専門員講座で培ってきた鳥獣害対策に関する知識を、生産者に共有するため、直売所(さいさいきて屋)で勉強会を開催した。

写真1 猟友会との現地確認

写真2 かんきつのイノシシ被害
3 活動結果
- (1)捕獲意識の向上に向けた取り組み
イノシシの足跡(写真3)や雑木林の切れ目となっている地形等を根拠に捕獲檻の移設を行った。移設後は、クラウドセンサーカメラを活用して誘引されている個体数や、餌付けの進み具合等をハンターに報告した。移設後に幼獣を計9頭捕獲することに成功した(写真4)が、成獣は警戒心が強く(動画1)、捕獲には至らなかった。

写真3 移設後の箱わな

写真4 捕獲されたイノシシ(幼獣)
- (2)防護意識の向上に向けた取り組み
①モデル園の設置
収穫開始前に、支柱の間隔を約3mとして、地面からの高さ15cm、2段張りで電気柵を設置した(写真5)。十分に電圧が流れていることを確認していたが、設置から数日後にイノシシが侵入していることが分かった(動画2)ため、3段張りとした。3段張りとして以降、1か月程度は被害ゼロとなっていたが、地際が広く開いた隙間からの侵入等により数果の被害を確認した。それでも対策実施前から被害は明確に減少した。
②鳥獣害対策勉強会の開催
直売所の生産者に、鳥獣被害の見分け方や対策の説明を行った(写真6)。今年は管内で特に鳥獣被害が多い年であったようで、対策未実施の生産者が半数以上を占めていた。

写真5 電気柵の設置

写真6 鳥獣害対策勉強会
4 考察と今後
- ○大西地区全体では、昨年より有害鳥獣の捕獲実績が減少しており、農作物被害増加の要因の1つとなっていると考えられる。特に昨年と比較して捕獲第1期(4月~6月)の捕獲数が減少しており、イノシシの出産期や、中型獣類の繁殖期にあたるこの時期が被害の増減に影響している可能性がある。
- ○地区内のハンターは果樹農家である方も多く、10月以降は農繁期と重なることから、当地区では、捕獲は4月~9月が適期にあたると考えられる。
- ○捕獲において、日頃の巡回や地域での情報共有が重要であることを学んだ。地区全体で捕獲効率を上げるためには猟友会と生産者の連携が必要であることから、管理専門員として両者の懸け橋となれるようにしたい。
- ○電気柵のモデル園地については、ある程度被害軽減効果が実証できたが、完全ではないため、今後も改善に取り組む必要がある。また、大西柑橘部会・キウイフルーツ部会にモデル園地での被害軽減検証結果を報告し、被害軽減対策の普及を行う。
- ○鳥獣害対策に関する勉強会は管内でこれまでに開催されてこなかったとのことで、参加者からはとても参考になった、今後も継続して開催してほしい等の前向きな反応があがった。今後も継続して対策技術の周知に取り組む。
参考動画(タイトルをクリックください。)
![]()

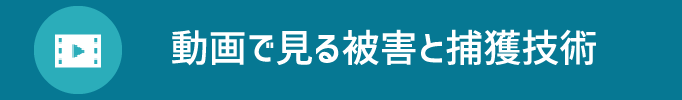
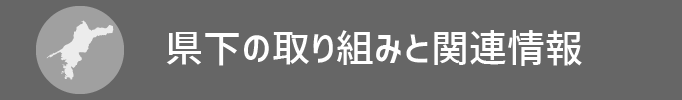
専門家の解説
イノシシの箱わなによる捕獲では、警戒心の低い幼獣ばかりを先に捕獲してしまうことで、成獣個体の警戒心がさらに高まり、なかなか箱わなに入らなくなることが知られています。
このため、警戒心の強い成獣個体を継続的な餌付けによって慣らしてから捕獲を実行することが特に重要なのですが、日々のエサやりには、相応の労力が掛かるため、捕獲者にわなの管理を一任していると、なかなかこうした根気のいる餌付けはできません。
問題の解決には、被害を受ける生産者自らが、わなやエサの管理を分担する補助者を活用した取り組みが不可欠となるため、堺専門員には、こうした捕獲の基本的な考え方や理屈の部分を、地元の捕獲者や生産者に伝え、地域の自衛力強化に繋げていただくことを期待しています。
また、捕獲の基本的な考え方や理屈の部分を伝えるうえで、センサーカメラによる動画資料やデータは、特に重要です。
昨年度はニホンジカによるものと思われるキウイフルーツの食害なども報告されていましたので、堺専門員には、被害の実態把握や対策の検討、技術の普及のため、根拠となるデータの取得に努めていただければと思います。
本事業でも、堺専門員はたくさんの映像資料を撮影し、報告会などで活用されていましたので、そうした技術や発表スキルを活かして、地域の被害対策促進に貢献していただくことを期待しています。